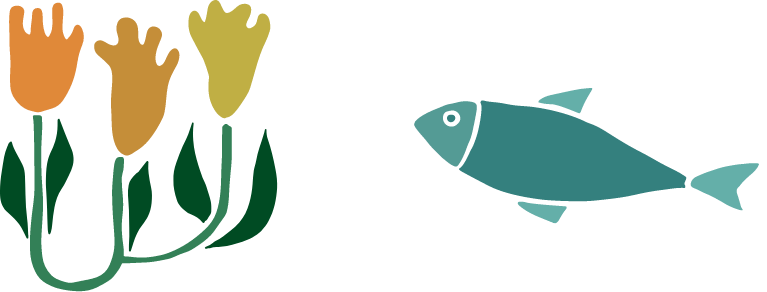01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
【連載】イラストレーター スズキトモコさんと三浦野菜の作り手を知り、伝えるデザインプロジェクト
Release2025.06.11
Update2025.12.06
【連載】イラストレーター スズキトモコさんと 三浦野菜の作り手を知り、伝えるデザインプロジェクト
Release2025.06.11
Update2025.12.06

三浦野菜の魅力を伝える「デザインプロジェクト」とは
地元良品JOURNEY三浦半島篇と鎌倉のテキスタイル研究所Casa de pañoとのコラボ企画「三浦野菜デザインプロジェクト」が始まります。三浦野菜の作り手や届ける仕事に携わる人にインタビューを行い、その魅力を「もよう」で表現します。完成したデザインはテキスタイル(布)となり、地元の人にも訪れた人にも長く愛される布製の日用品に展開します。
デザインは、旅行ガイドブック「ことりっぷ」を始め、広告や絵本などのイラストレーションを手掛けるイラストレーターのスズキトモコさんが担当します。
『三浦の大根もよう』の物語
『本春キャベツもよう』の物語
『三浦のスイカもよう』~美味しい秘密~
『三浦のかぼちゃもよう』~こだわりかぼちゃのの美味しい秘密~
みうら夜市でデビュー!畑取材から生まれた、三浦野菜のキッチンタオル
三浦野菜もようを纏う。生産者の物語と繋がる「三浦野菜もようのキッチンタオル」発売開始
Designer

Writerいとうまいこ
大学卒業後、大手家電メーカーで商品企画や展示に関わる。そのときの経験からテキスタイル(布)に関わる仕事をしたいと考え、2023年にテキスタイルのギャラリー「Casa de paño」を鎌倉で開業。展覧会やワークショップの企画に加え、三浦半島の豊かな自然や生き物、暮らしをモチーフにした布製品の商品企画を行っている。本企画は、三浦半島で暮らす人・営む人へのインタビューをもとに、もようのデザインを通して地域の魅力を再発見し共有する試みです。


RECOMMEND

RANKING



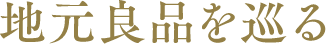
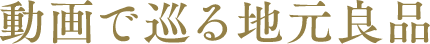
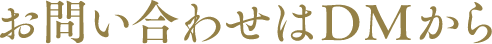















.jpg?q=60&w=1059&h=696&fm=webp&dpr=1 1x)




.jpg?q=60&w=1454&h=836&fm=webp&dpr=1 1x)
.jpg?q=60&w=795&h=501&fm=webp&dpr=1 1x)